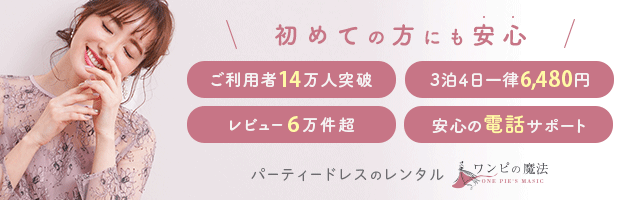結婚式に招待されたとき、悩みやすいのが「ご祝儀はいくら包むのが正解?」という点です。
ご祝儀は友人や親族、上司など、新郎新婦との関係性によって相場は変わりますし、夫婦や子ども連れで出席する場合にも目安があります。
お祝いの気持ちを表す大切なものだからこそ、マナーを押さえてスマートに準備したいですよね。
そこで今回は、
- 新郎新婦との関係性別の金額相場
- ご祝儀の渡し方
- 注意したいポイント
などを分かりやすく解説します。
結婚式にお呼ばれされた方、ご祝儀についてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
結婚式のご祝儀、相場の金額はいくら?
結婚式のご祝儀は「いくら包むべきか」が一番の悩みどころ。
新郎新婦との関係性によって相場が変わるため、まずは基本の金額感を押さえておきましょう。
ご祝儀の定義や関係性に応じた相場を解説します。
ご祝儀とは
ご祝儀とは、結婚式に招待されたゲストが新郎新婦へ贈るお金のことです。
単なる「出席料」ではなく、お祝いの気持ちを表す大切な心づけとして位置づけられています。
包む金額には、新郎新婦との関係性や立場によって目安があり、友人や同僚、上司、親族などで相場が変わります。
ただ、あくまでも相場は目安なので、お祝いのお気持ちであるため、厳密には「いくら包めばOK」かは決まっていません。
また、ゲストが負担する食事代や引き出物代も含まれると考えられており、あまりに少なすぎる金額は失礼にあたることも。
逆に高額すぎると新郎新婦に気を遣わせてしまう場合もあるため、注意が必要です。
ご祝儀は「お祝い」と「配慮」の両面を兼ね備えた習慣であり、結婚式に参加する上で欠かせないマナーといえるでしょう。
ご祝儀の相場は?新郎新婦との関係別に紹介
ご祝儀の金額は、新郎新婦との関係性によって変わります。
友人や同僚、親族、上司など立場ごとに相場があるので、自分に当てはめて考えるのが安心です。
以下は一般的な目安です。
| 新郎新婦との関係 | ご祝儀の目安金額 |
|---|---|
| 友人・同僚 | 3万円 |
| 上司・部下 | 3万円(上司からは5万円の場合も) |
| 兄弟姉妹 | 3~5万円(状況により10万円) |
| 叔父・叔母 | 5万円 |
| いとこ | 3万円 |
| その他の親族 | 5~10万円以上 |
| 取引先関係 | 3万円 |
友人や同僚は「3万円」がもっとも一般的で、全国調査でも平均は3万円前後という結果が出ています。
上司や目上の立場からは、3万円に加えて5万円を包むケースも。
親族は幅が広く、兄弟姉妹なら3~5万円、叔父叔母は5万円が目安ですが、新郎新婦と年齢が近いなど立場によっては3万円程度に収めることもあります。
祖父母や両親といった近しい親族の場合は、10万円前後と高額になるケースもあるでしょう。
このように金額には幅がありますが、実際には「3万円」が基準として選ばれることが多いです。
立場や年齢に応じて少しずつ調整しながら、無理のない範囲で準備してみましょう。
基本の相場は3万円
結婚式のご祝儀は立場によって幅がありますが、もっとも多いのは「3万円」です。
友人・同僚・親族・上司など多くの関係性で選ばれており、迷ったら3万円を包むのが無難と覚えておきましょう。
ご祝儀2万円はマナー違反?
ご祝儀は「偶数=割り切れる=縁が切れる」と考えられてきたため、2万円は基本的に避けたい金額とされています。
ただ、2万円は「ペア」として考えることもできるため、10代~20代前半など社会人歴が浅い場合や、挙式のみ参加する場合などは2万円でも問題ないとされるようになりました。
一方で30代以上や、親族・上司といった立場では2万円は失礼と受け取られる可能性が高く、避けたほうが安心です。
どうしても2万円を包むときは、1万円札+5千円札2枚といった工夫をするとよいでしょう。
夫婦や家族で参加する場合のご祝儀はどう渡す?
夫婦や子ども連れで結婚式に出席する場合、ご祝儀は「人数分をまとめて」包むのが基本です。
立場や関係性に応じて金額の目安が変わるため、それぞれの場合を確認しておきましょう。
夫婦の場合
夫婦で結婚式に招待された場合は、2人分をまとめて包むのが基本です。
ご祝儀の相場が1人3万円が基本のため、「2人分で6万円」と考えられがちですが、割り切れる偶数は避けたほうが無難です。
そのため相場は5万円が目安で、親族や上司の式など立場によっては7~10万円にするケースもあります。
夫婦で出席する場合は、一つのご祝儀袋にまとめるのが一般的です。
表書きは代表名だけでもよいですし、夫婦の名前を並べて書いても構いません。
いずれの方法でも失礼にはあたりませんので、分かりやすい形で記すと安心です。
子ども連れの場合
子どもを連れて結婚式に参加する場合、ご祝儀の金額は「子どもの年齢や席・料理の有無」で変わります。まだ乳幼児で料理や席を特別に用意しない場合は、夫婦分のご祝儀のみの「夫婦で5万円」を基準にしておけば安心です。
一方、子ども用の料理や引き出物が準備されている場合には、1人あたり1~2万円程度を加算するのが一般的です。
ただし、人数分をすべて換算して包む必要はありません。相場の目安を考えながら、調整しましょう。親族や友人などの立場や地域の慣習によっても変わるため、あくまで「お祝いの気持ち」を優先して無理のない範囲で包めば十分です。
会費制の結婚式にご祝儀は必要?
会費制の結婚式では、会費のみを支払えばOKで、基本的にご祝儀は不要です。
「ご祝儀不要」と招待状に書かれている場合は特に、会費以外を持参する必要はありません。
ただし案内がなく、親しい友人や親族として出席する場合には、1万円程度を添えるケースもあります。
ご祝儀を渡すときの一般的なマナー
ご祝儀は金額だけでなく、渡し方にも気を配ることが大切です。
袱紗で包む、ご祝儀袋の選び方、新札を用意するなど、基本的なマナーを押さえておくと安心です。
袱紗(ふくさ)について
ご祝儀はそのままバッグに入れるのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。
袱紗は大切なお金を清潔に保ち、格式を重んじる意味もあります。
色は慶事用の赤や朱、紫などを選ぶのが基本で、弔事用の黒や灰色は避けましょう。
受付で渡す際は、袱紗からご祝儀袋を丁寧に取り出して手渡すとスマートです。
ご祝儀袋について
ご祝儀袋は、贈る金額や相手との関係性に合わせて選ぶのがマナーです。
友人や同僚へのご祝儀ならシンプルなデザインやデザイン性のある水引も良いですが、上司や親族など目上の方の式では豪華な水引のものを選ぶと安心です。
表書きは「寿」「御結婚御祝」とし、濃い墨で丁寧に書きましょう。
名前はフルネームで記入するのが基本です。
 |  |
| 花言葉を添えて贈る、満開の花束を描いた華やかな金封ご祝儀袋。ブルースターの花言葉は:幸福な愛。 | 古くから縁起物として親しまれてきた「鶴」の水引飾りに、上品で華やかなパールのような光沢あるゴールドの檀紙と友禅紙が組み合わさったデザイン。 |
ご祝儀は新札で
ご祝儀には新札を用意するのがマナーです。
「新しい門出を祝う」という意味が込められており、折れや汚れのあるお札は失礼にあたることもあります。
銀行で事前に新札へ両替できますが、直前は混み合うこともあるため、余裕をもって準備しておきましょう。
新札を袱紗に包んで渡すことで、より丁寧なお祝いの気持ちが伝わります。
結婚式は欠席だけどご祝儀を渡したい!という時は
結婚式に招待されたものの、やむを得ず欠席する場合でも「お祝いの気持ち」を伝えるのが大切です。
欠席の連絡をする際に一言「後日お祝いをお渡ししたい」と伝えると丁寧な印象になります。
ご祝儀を渡す場合は、出席時と同じ金額でなくても構いません。
友人や同僚なら1万円、親族なら1~3万円程度を目安にするのが一般的です。
招待状の返信を出した後や式の前日など直前に渡すのは避け、式の1~2週間前までに現金書留で送るか、直接手渡しするのが安心です。
一方、欠席の理由が出産や遠方などで「ご祝儀を包むのが負担」という場合には、プレゼントを贈る方法もあります。
新郎新婦が好みに合わせて選べるようなカタログギフトや実用的なペアグラスなどが人気です。
大切なのは金額よりも「祝う気持ちが伝わること」。
欠席するからこそ、心を込めた形でお祝いできると好印象です。
ご祝儀だけでなくプレゼントも渡したいときに気を付けること
ご祝儀に加えてプレゼントを贈りたい場合は、金額や渡すタイミングに注意が必要です。
気持ちが伝わる反面、相手に負担をかけすぎないよう、いくつかポイントを押さえて準備しましょう。
プレゼントの金額相場
ご祝儀に加えてプレゼントを贈る場合、金額は5,000円~1万円程度が一般的です。
あくまでご祝儀がメインとなるため、高額すぎる品は新郎新婦に気を遣わせてしまいます。
親しい友人や同僚にはペアグラスや日常使いできる家電、親族にはカタログギフトなど、実用性のある品を無理のない範囲で選ぶと喜ばれます。
プレゼントの渡すときの注意点
ご祝儀に加えてプレゼントを贈るときは、渡すタイミングに注意しましょう。
結婚式当日に持参すると荷物が増えて新郎新婦の負担になるため、事前に自宅へ郵送するのが基本です。
式の1週間前~前日までに届くように手配すると安心です。
また、プレゼントの内容にも気を配りましょう。
刃物やハンカチなど縁起が悪いとされる品は避け、生活に役立つ実用的なものを選ぶのが無難です。
サイズや色など好みが分かれるものより、カタログギフトや人気ブランドの定番アイテムが喜ばれる傾向にあります。
金額以上に“祝う気持ち”が何よりの贈り物です。
無理に高価な品を贈る必要はなく、相手の負担にならない範囲で準備してみましょう。
結婚式当日に必要なものをチェック
結婚式当日はご祝儀だけでなく、必要な持ち物を整えておくと安心です。
ただしフォーマルバッグは小ぶりなものが基本なので、最低限の必需品だけを入れ、残りはサブバッグに分けるのがおすすめです。
必須アイテム
- ご祝儀袋(袱紗に包んで持参)
- 招待状・式場の地図など
身だしなみアイテム
- ハンカチ・ティッシュ
- 替えのストッキング
- メイク直し用の小物
あると安心なもの
- モバイルバッテリー
- 折りたたみ傘(天候が不安な場合)
小さなバッグに詰め込みすぎると見た目の印象も損なわれるので、「式場内は最小限・その他はクロークへ」が基本。
前日までに荷物を整理しておきましょう。
結婚式におすすめの袱紗
結婚式におすすめの袱紗をご紹介します。
アイテムは実際にレンタルOK!気になる商品をぜひチェックしてみてくださいね。
上品なレース袱紗で大人可愛く
やわらかなカラーは上品さもあり、友人や同僚の結婚式にぴったりです。
派手すぎず程よく華やかなので、年代を問わずおすすめできます。
お揃いのサブバッグと合わせて持つのもおしゃれですよ。
 |  |
| サテン地にフラワー刺繍のチュールを重ねたベージュのふくさ。立体感のある大柄の刺繍にはゴールドの糸が施され、上品で華やかな雰囲気に。 | 所々ラメの刺繍が施されていてるので華やかな印象に。個性的な刺繍はコーディネートのポイントに。 |
華やかピンクゴールドで可愛さと上品さを両立
繊細な刺繍レースにリボンをあしらった、女性らしい印象の袱紗です。
落ち着いたピンクゴールドは甘すぎず、上品さもあって◎。
友人や親族の式など幅広く使え、大人っぽさを演出したい方のスタイルともマッチします。
格式高い紫のちりめん袱紗で落ち着いた印象に
ちりめんならではの柔らかな風合いに花柄をあわせた、落ち着いたデザインの袱紗。
紫は慶事・弔事どちらにも使える万能カラーなので、一枚持っておくと便利に活用できます。
特に親族や上司の結婚式など、フォーマルな場にふさわしい雰囲気を演出したい方におすすめ。
信頼感のある印象を与えてくれます。
まとめ
ご祝儀は金額だけでなく、気持ちやマナーも大切。
関係性やシーンに合った準備を整えて、安心して当日を迎えましょう。
袱紗など小物もチェックしておけば、立場に合わせた適切な振る舞いで結婚式をお祝いできますよ。